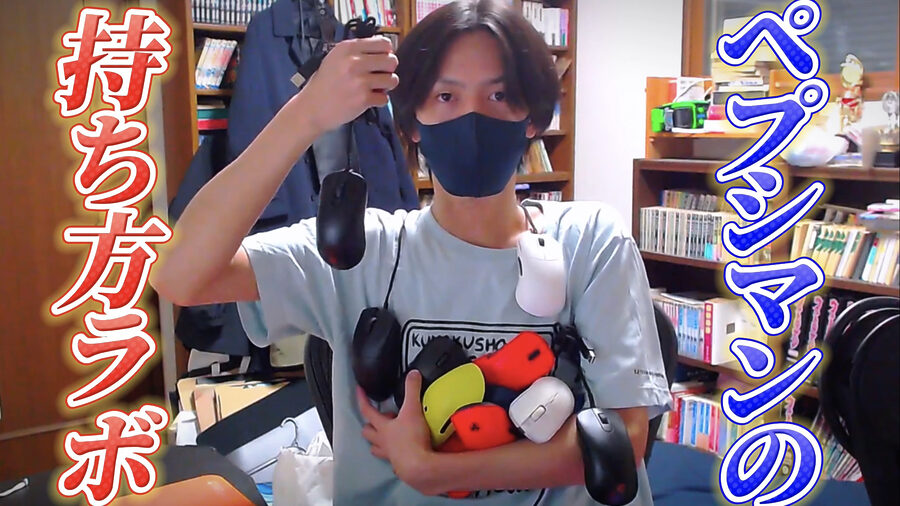【コラム】ペプシマンの持ち方ラボ 定期連載第二回
[寄稿者:PepsiMan_ax]
こんにちは。
連載頻度が「ワンパンマン」とほぼ同じでおなじみ、持ち方ラボのお時間です。
前回はたくさんの方にお読みいただけたようでして、読者の皆さまに感謝申し上げるとともに、非常に安堵する次第です。今後とも良質な記事執筆に最善を尽くしますので、どうぞごひいきに。
今回は、いつの間にかプロシーンを席巻していた「あのマウス」について、持ち方の観点から、定着理由を考察して行きます。

変化-change-
「変化」と聞いて、読者の皆さまは何を思い浮かべますでしょうか?
時代の移ろい、人の成長、「Viper V2 Pro」と「V3 Pro」の形状差…
能動的なことであっても、受動的なことであっても、これらはひとまとめに変化と呼ばれます。
これ自体に良し悪しはなく、この世界に存在するものであれば何にでも起こりうる、とても自然なことです。
ゲーミングギアの業界においても、変化という概念は切り離せません。
特に近年のリリース頻度向上は、マンネリ化も速まるということですので、メーカーは新製品毎に大なり小なり変化をつけ、常に話題を作り続けています。
特に顕著だと感じたのは、先述のRazer Viper V3 Proです。
初代→Ultimate→V2 Proと続いたViperシリーズといえばこれというフォルムを大きく崩し、当時のトレンドであった「くびれケツデカ形状」を採用。(正確には、ProではなくHyperSpeedが先にリリースされました)
Zekken選手が先行使用中にMasters優勝を成し遂げたこともあり、多少不安視された部分もありましたが、現在ではLogicool G PRO X Superlightと双璧をなすマウスへ成長しました。
これは、Viper V3 Proが二つの変化をもたらしたとも言えます。
一つは先述の通り、デバイス使用率の変化。
そしてもう一つが、持ち方の変化です。
「G PRO X」の牙城
Logicool「G PRO X」シリーズ。
これほどまでに爆発的人気を誇り、支持を集めるマウスといえばコレです。
エルゴノミクスマウスを使っていたとしても、逆ハの字のマウスを使っていたとしても、穴の開いた軽いマウスを使っていたとしても、人類は最終的にG PRO Xをメインに据えることになります。
あのTenZ選手ですら逃れられなかったのですから、一般ゲーマーの我々が逃れられるわけがありません。
G PRO Xのシェアを集める理由に、スポンサーの影響や、市場シェアなどを挙げる方がいらっしゃるかもしれません。確かに否定はできませんが、これらには明確に反論できる点があります。
- 「市場に良いマウスがあまり出回っていない時代だったから」について。
2023年ごろから「VAXEE」や「G-Wolves」などの比較的後発のメーカーがシェアを伸ばし、脱「G PRO X」の流れができているかのようにみえました。
しかし、一年の集大成である「VCT champions Los Angeles」の使用マウスではG PRO Xがシェア率一位。
グランドファイナルに絞っても、10人中4人がG PRO Xユーザーです。
また、全champions優勝チームには、必ずG PRO Xユーザーが所属しています。
- 「スポンサーの影響」について。
これはチームにもよりますが、基本的に、マウスはある程度自由に選べる傾向にあります。
例えば、Logicool(Logitech)と密接なコネクションがあるNatus Vincereに所属する選手ですら、ZOWIEやRazer、Finalmouseなどのマウスを長期にわたって使用していた時期がありました。
他にも、Karmin Corp・TH・FUT・G2など、特に関わりの深いチームに所属する選手ですら、他企業のマウスを積極的に使用。
マウスパッドにはスポンサー配慮のためにマスキング用のテープが貼っていることもありましたが、マウスに関しては比較的制約が緩いことが見て取れます。
つまり筆者(PepsiMan_ax)が考えるには、G PRO Xは、市場シェア、スポンサーの影響でもなく、自力でその地位を獲得した可能性が非常に高いのです。
持ち方の観点から見ても、G PRO Xはとても優秀なマウスであることが分かります。
くびれや突起のない、非常にシンプルな表面。
サイズ感も、指を固定しやすく自由にさせやすい絶妙なバランスであり、研究すればするほど良いマウスであることが分かるのです。
もうひとつのライバル「毒牙」
「Viper V3 Pro」は、前述の「G PRO X」と双璧をなす人気マウスです。
Viper V3 Proの最も優れた点は、その「大きさ」にあると考えています。
今日に至るまで、中央部分にくびれを有したマウスは沢山リリースされてきましたが、そのどれもがシェアを大きく占めるには至りませんでした。
原因の一つに、それらの縦のサイズが小さめであったことがあると思います。
小さめといっても、大半の日本人ユーザーにとってはぴったりサイズに近く、分類としてはミディアムに属します。
しかし、様々な国で使われるためには、様々な人に使われるためには、ある程度の長さが必要です。
持ち方を作る上でぶつかりやすい壁が、指を自然に配置できる範囲が限られていること。
特にこれは側面で起きやすい問題で、短いマウスでは狭いスペースにすべて指を納めなければいけないため、どうしても無理の出る箇所が発生します。
くびれのあるマウスは、指のハマり具合をマウスが先導して作ってくれるため、これを解決できるように思えるのですが、結局のところ十分なスペースが存在しないため、根本の解決には至っていません。
また、縦を短くすると、全体のバランスを取らねばならない都合上、横幅もそれなりに狭くなります。
そうなると、例えば手の皮の伸び具合を重視する持ち方や、指を伸ばしつつ、しっかり側面にはめ込む持ち方との相性をとても選ぶことになります。
しかしViper V3 Proは、縦の長さが127mmあるため(G PRO Xは125mm)、必然的に横幅が確保しやすくなり、特有のケツのふくらみも相まって、自由度が高いのにしっかりとした張り具合を確保できるのです。
上記二つの条件を有した持ち方をしているEDG Smoggy選手は、リリース以降ずっとViper V3 Proを使用していることからも、このサイズ選びは成功していることが分かります。
毒蛇(Viper)の毒牙が長いことから着想を得ていたら激アツですね。
ハリの質とプレイヤーの変化
さて、ViperとG PRO Xの形状がいかに素晴らしいかを理解していただいたところで、メタの概念を加えます。
第一回で触れたように、プロシーンでは23年以降、ハリメタが続いています。

このハリに関して、実は二種類の発生方法が存在する可能性があるのです。
一つは自発的に発生させるハリ。
ZywOo選手の親指・人差し指や、donk選手の小指側手の平の事例がこれに該当します。
つまり、意図的にハリを発生させる形状を作り、そこにマウスをはめ込むといった手順を踏んだものですね。
もう一つは受動的に発生するハリ。
例えば、マウスのケツが手の平に大きく接触した際、マウスからの圧力で皮が広げらるものが該当します。
要は、意図せずに発生するハリのことです。
23年のプレイヤーは、前者のハリを有する割合が高かったように思います。
前回例に挙げた選手だけでも、Jinggg選手・Less選手・Demon1選手は確実に該当しています。
しかし24年後期~現在までに活躍した・しているプレイヤーは、後者の割合が増加してきました。
分かり易い選手として挙げられるのは、DRX Flashback選手。
彼の指配置はかなり一般的なものと近く、ハリを発生させる形状は含まれていないと考えています。
しかし彼の持ち方を再現すると、確かに手の平にハリが発生していることが分かります。
これはViperのケツによって手の平の皮が広げられ、結果的にそれが固定力の増強を行っている、という図式が発生しています。
もう一人例を挙げるなら、DFM gyen選手。
彼の持ち方も、あまり能動的にハリを発生させる形は見られないのですが、手の接触部位が点在しており、それがマウスの両端にあるため、結果少しだけハリが発生します。
シーズン開幕1か月を切ってのマウス変更だったので、かなり思い切ったことをするな、と思いましたが、この変更はどうやら今のところ上手く行っているようです。
この受動的に発生するハリに関して、G PRO Xでは得ることが困難です。
というのも、これはケツに幅があるだけでは発生しにくく、指をすぼめさせるための装置との相乗効果で初めて発揮されるもの。
G PRO Xは絶壁であるため、たとえ指を曲げ手の平を押し付けても、発生するハリはたかが知れています。
まとめると、受動的なハリを主軸とした持ち方のプレイヤーが台頭してきたタイミングで、相性のが良いとされる、くびれを有した大きめサイズのViper V3 Proがリリースされ、それにぶっ刺さった人がこぞって乗り換えた結果が現状。という話ですね。
サラッと”乗り換えた”と書きましたが、シェア率を獲得した背景に、もう一つ面白い事象があります。
実はG PRO X→Viper V3 Proという図式のプレイヤー以外にも、別のマウスからViperに乗り換えた人も少なくないのです。
代表例だけでも
- T1 BuZz選手 (ZOWIE S2)
- T1 iZu選手 (Finalmouse UltralightX)
- ZETA Dep選手 (Viper V2 Pro)
- M8 Zyppan選手 (DeathAdder V3 Pro)
など多種多様で、これらのマウス使用者を取り込んでシェア率を伸ばした、という見方もできます。
これはViper V3 Proの持つ「ぶっ刺さる人にはぶっ刺さるが、当たり判定が大きいため、かなりの人に刺さってしまう」という特徴がよく表れた結果です。
つくづく面白いマウスだと思いますね。
おわりに
私自身は、二大マウスのうち「毒牙」を推します。このマウスの魅力に憑りつかれた人間の一人で、発売日に手に入れてから半年はずっとメインに据えていました。
持ったときの衝撃もさることながら、触り続けるうちに分かってくる良さなどもあり、この一機で持ち方に対する考え方はかなり変わったような気がします。
まだ所持していない方はもちろんのこと、買ったけど使ってないよ、という方も、この機会に是非手に取ってみてください。
きっと「マウスから滋味を感じる」ほどの摩訶不思議な体験ができるはずです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
面白いと思っていただけたら、Xのフォロー、YouTubeのチャンネル登録を是非お願いします。